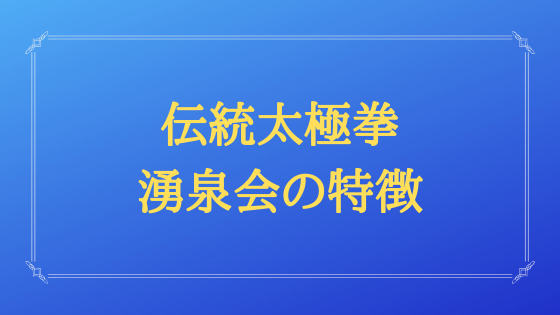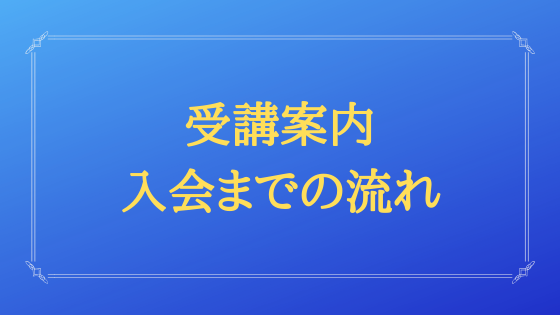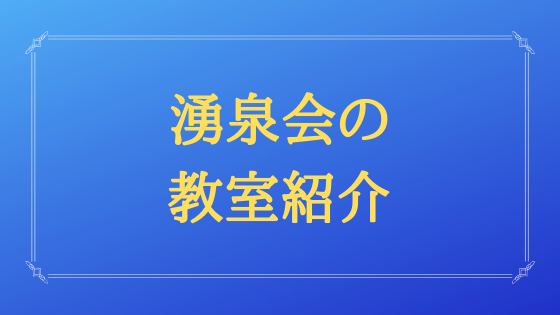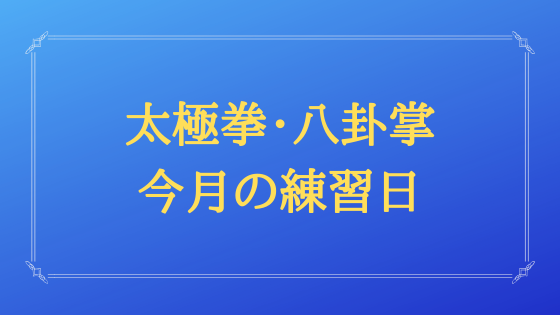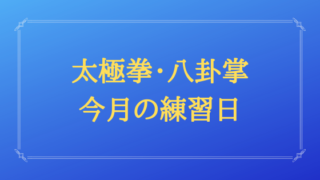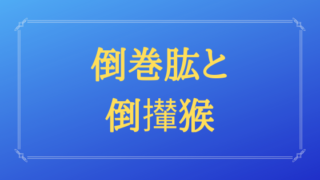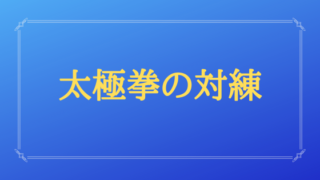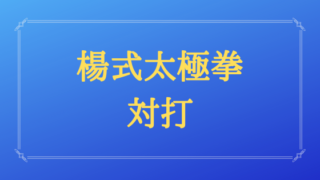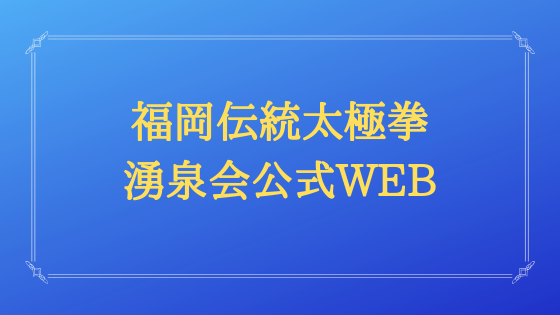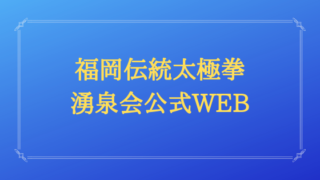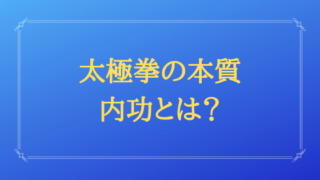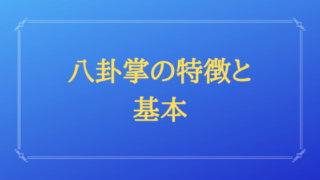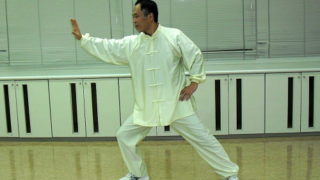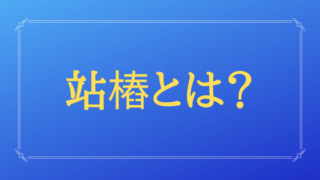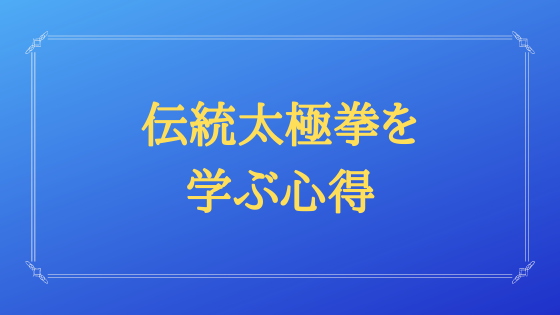
伝統の太極拳や八卦掌を本格的に学んでいくのであれば、知っておきたい知識や心得といったものがあります。
といっても、難解な陰陽理論や太極拳譜を事前に読み込んでおかなければならないという訳ではなく、中国武術独特の習慣や決まり事の事です。
本ページでは、当会の練習体系の根幹を教えて頂いた先生の教えを中心に、私自身が学んでいた時に感じた疑問点や、逆に指導をしていて気付いた事を紹介しています。
Contents
自分の目的や目標に応じた師を選ぶ

これから太極拳や中国武術を学ぶ方は、まず自分自身がどのような目的や目標を持っているのかを具体的に考えてみましょう。
なぜなら、その理由や目的に応じた師を選ばないと、結果として自分の目的に向かっての指導が受けられないからです。
例えば、少し運動したいという理由であれば、自分の家の近くの太極拳教室で構わないと思います。
将来的に表演の大会に出たいのであれば、全日本武術太極拳連盟に所属している教室を選ぶ必要があります。
散打(組手)の大会に積極的に参加したい場合は、やはり散打練習を中心に行っている団体を選ぶべきです。
私自身は伝統武術としての太極拳や八卦掌を指導している先生を選んで学んできました。
その場合は、まず先生の動きと人柄、そして、どのような練習体系が伝わっているかが重要だと思います。
変に神秘的な思想に偏らず、現実的な指導をされている教室は、まだまだ非常に少ないと思います。
武術の世界では、「三年掛けても、良師を探せ」との言葉もあります。
しっかりと情報を集めて、自分が学ぶべく師を探されると良いと思います。
門派(教室)選びのアドバイス
私自身の経験を基に、教室や先生を選ぶ際のアドバイスを掲載します。一つの助言としてご参考下さい。
- あまり多くの拳種を指導している教室は避ける
- 肩書や地位に惑わされない
- SNSの情報を鵜呑みにしない
① 教室案内などで、非常に多くの拳法を指導している教室があります。
確かに色々な拳法を体験できるという点では良いような気もします。
ただし、私自身の経験で言えば、一つの拳法の本質を理解し、習得するだけでも十年以上の年月はかかると思います。
また、それぞれの拳法で要訣や身法が異なるため、実質的に一人の人間がいくつもの拳法を習得するというのは、あり得ないでしょう。
実際、同じ内家拳のカテゴリーである太極拳と八卦掌でもずいぶんと違いますし、太極拳同士でも流派が異なれば、細かい部分は異なってきます。
広く浅く多くの拳法を学びたいのであれば構いませんが、深い段階まで学びたいのであれば、多くの拳法を指導している教室は避けたほうが良いと言えます。
② 日本人は昔から肩書に弱く、何代目宗家とか、何代目伝承者とか言われると、すぐに信じてしまいます。
もちろん、名誉のある門派で学んだ事は、価値のある事だと思います。
ただし、武術というものは、最終的に その個人が、どれだけ深く練習してきたかがすべてです。
例えば、伝人と言っても、2~3年習っただけの人もいれば、10年以上学んだ方もいるでしょう。ひどい例としては、数回習っただけでも老師の名前を出している方もいます。
肩書上は、その全てが伝人を名乗っている場合もあります。
肩書ではなく、実際に自分の目で見て、その先生の話を聞いて、納得いく先生を選びましょう。
③ 私が中国武術を学んできた時代と、現在で一番違うのは、SNSの普及だと思います。
実際、Xやyoutubeの更新を日々楽しみにしている武術愛好家の方も多いでしょう。
そういった方々に、一言だけ助言するとすれば、本当に高い次元の武術の技は、見ても分からないという事です。
理由は、武術本来の技法は、相手の意識や感覚に作用し、意や内功の動きで操作しますから、外見からはほとんど見えなくなります。
そこに、迫力といったものはありません。
映像のプロを雇ってまで、彼らがなぜ動画をあげているのか、一度考えてみるとよいと思います。
中国武術は一対一の徒弟制、道場はその集合体

何か習い事を始めようと思ったら、その習い事を指導している教室を探して学ぶのが一般的だと思います。
太極拳の場合であれば、太極拳の教室を探して、その教室に入会して学ぶのが普通でしょう。
それに対して、伝統の中国武術の場合は、教室に入会するというよりも、その先生個人に入門するといった感じになります。
その先生に対して、各個人が入門し、入門した一人一人と、その先生の師弟関係の集合体が教室だったり、門派だったりする訳です。
日本的な感覚で言えば、歌舞伎や日本舞踊の家元に入門するとか、陶芸の窯元に入門するとか、そういう感覚に近いと思います。
もちろん、そういう教室はごく一部ですので、一般的ではないですが、伝統の門派に入門する場合は、そういった心構えが必要となります。
功夫は、師と弟子の共同作品

功夫と言うと、カンフー、中国拳法の総称として受け取る方が多いと思います。
功夫の本当の意味は、時間と工夫を積み重ねる事で得た能力や技術の事を言います。
つまり、仕事ができる熟練の職人さんに対して、あの人は功夫があるというような使い方をします。
職人の世界と、武術の世界は、非常に似ています。
職人の世界でも武術の世界でも初心者は、文字通りひよっこです。
それこそ、親方が手取り足取り教えてあげないと、何もできません。
その何もできない人間を、一人前に育て上げていくのが師です。
太極拳の場合も、内功などの本質的な部分まで指導するとなると、先生のほうでも大変な作業を請け負う事となります。
また、生徒のほうでも、こちらの指示や方針に全面的に従ってもらう必要があり、それに対応できる環境を作り、真摯に取り組んでもらう必要もあります。
つまり、功夫は、親方と弟子の共同作業です。
親方のほうが一所懸命でも、弟子のほうが、それほどやる気がなければ、功夫は完成しないでしょうし、
弟子のほうに、すごくやる気があったとしても、先生のほうが忙しくて時間が作れなかったり、教える気がなければ、同じ結果となります。
学ぶ側が良い先生を求めているのと同じように、先生のほうでも良い弟子を求めています。
では、良い弟子とは何かと言えば、自分と同じ価値観を持って学んでくれる人、取り組んでくれる人という事になるでしょう。
いずれにしろ、一人の人間が本気で教えられる(育て上げる)人数は、限りがありますから、その中でどう認められていくかは自分次第です。
伝統の中国武術を学んで感じたこと
ここからは、私個人が伝統の太極拳や八卦掌を学んでいて感じた事、また入門後に師から教わった言葉を中心に紹介します。
学ぶとは、入門するとは
まず、入門するという事が具体的にどういう事なのかを考えてみましょう。
具体的には、以下の2点が挙げられると思います。
- 先生に自分を教える時間を作ってもらうという事
- その時間は、本来は先輩達が学んでいる時間を分けてもらうという事
① の先生に教える時間を作ってもらうというのは、誰でも分かると思います。
私も学びたいという方がいて、その方に教えたいと思えるかどうかで、時間を作っています。
しかし、②の自分の教えてもらう時間は、先輩達が学んでいる時間を分けてもらうという感覚は、一般的には無いと思います。
例えば、あなた(初心者)が教わる時間を1時間作ってもらったとしましょう。
そこに新たな入門者が一人増えれば、あなたが先生から学ぶ時間は、半分の30分となります。
3人になれば、20分。6人なら10分という事になります。
つまり入門者が増えれば増えるほど、あなた自身の学べる時間は減るという事です。
あなた自身の学ぶ時間を分けてあげているにも関わらず、その入門者が先生や指導方針に対して不満ばかり言っていたら、あなたはどう思うでしょうか?
武術や芸事の世界では、礼儀や学ぶ姿勢が重視されますが、自分の学ぶ時間は、先生や先輩達が作ってくれていると思えば、自然と感謝の気持ちを持つ事ができるのではないかと思います。
中国武術の基本は、身体を動かす仕組み(内功)を作る
一般的な武道や格闘技でいう基本は、突き技だったり、蹴り技だったり、受け技であったりと、所謂、基本的な技から学び始めるのだと思います。
それに対して伝統の中国武術、特に内家拳と言われる太極拳や八卦掌の場合は、一見すると、技とはまったく無関係な練習から始まります。
典型的なものは、站樁(たんとう)や八卦掌の走圏でしょう。その他、歩き方や重心移動を学ぶ歩法、内家拳独特の力の出し方を学ぶ基本功などもあります。


言い換えると、この基礎的な部分が正しく伝わっておらず、最初から套路(型)を学ぶような教室では、功夫は身に付かないと思います。
理由は、伝統の太極拳や八卦掌の練習体系は、この段階で学ぶ基本功を発展させる事で、套路や技法といったものが存在しているからです。
当会で長年学んでいる方は、実際に実感されている事だと思いますし、後に学んだ陳式太極拳の教室でも同じでした。
また、鄭志鴻老師に太極拳を学び始めた時は、站樁と歩法のみを数ヶ月かけて学びましたし、八卦掌は、走圏のみを一年半かけて学びました。
当時は「こんな練習が何の役に立つのだろう?」と、疑問に感じましたが、結果的には、それが一番の近道だったと思います。
当会の練習体系の詳細は、【伝統太極拳の基本と練習体系】のページをご覧下さい。
道場は学ぶ場、練習は自分自身で

この言葉は、当会で学んでいる方には、入門時に説明をしています。
一般的なスポーツや武道の場合は、その練習場所(ジムや道場など)に行って練習するのが普通だと思います。
それに対し、太極拳や八卦掌などの中国武術の場合は、道場は学ぶ場、あるいは確認をする(してもらう)場であり、練習は自分自身で行うといった認識が必要となります。
理由は、太極拳や八卦掌は、内功という特殊な仕組みを体の中に作る事(一人稽古)が、少なくとも練習の初期段階では、根幹となるからです。
内功についての詳細は、こちらのページで紹介しています。
道場と自宅での練習図
とはいえ、最初からそんな事ができる訳ではなく、当初は外見上の形を整える(学ぶ)事から入ります。
具体的な手順としては、以下の通りです。
- 道場で学び、覚える
- 自分で復習する
- 自宅で復習して、曖昧なところを、道場で確認する
- 確認した上で、量的な稽古を行い、習慣化する
① 道場で学び覚える
③ 自宅で復習して、曖昧なところを、道場で確認する
② 自分で復習する
④確認した上で、量的な稽古を行い、習慣化する
道場と自宅での練習を交互に繰り返す事で、一つ一つの動作を自分自身で練習できるようにするのが、初心者の目標の第一歩です。
※ 道場で覚えられなければ、休憩時間にメモを取るようにしましょう。
また、このサイクルを習慣化する事で、太極拳が日常の一部となっていきます。
当会の具体的な練習体系については、こちらのページでご確認下さい。
成果を持ってこなければ、時間の無駄
今時、教室でこのような事を言っていたら、誰も通って来なくなると思いますが、私自身は「成果がないなら、練習に来るな」と、よく言わました。
当時は、ずいぶん厳しい言葉だと思っていましたが、実際に自分が教室を20年以上やってきて、身に染みる言葉です。
「道場は学ぶ場、復習する場」であると共に、先生に前回学んだ内容を確認してもらう場でもあります。
その際に、前回指摘された注意点や改善点が、全く改善されていない場合は、先生のほうでも指導のしようがないという事です。
進歩のない状態な訳ですから、学びに来た学ぶ側にとっても、教えに来た教える側にとっても、時間の無駄という事になります。
「忙しくて、全然練習できない」という方もいますが、こういう方の場合は、道場が学ぶ場ではなく、練習する場になっているんですね。
つまり、上記で紹介した「道場は学ぶ場、練習は自分自身で」ではなくなっているという事です。
そうなると、必然的に入門時期が同じでも、そこに習熟度の差というものが生じてきます。
武術を学ぶ場合は、基準に達しているかどうかが、先に進めるかどうかの基準となります。
ですから、基準に達していない場合は、道場に来てもなかなか先に進めないという事になります。
私自身が教えていても、教室に来れば、先の動作を教えてもらえると思って来る方がいますが、成果が上がっていない状態では、教えようがないというのが実情です。
いずれにしろ、学ぶ立場としては、最低限、前回学んだ内容を復習し、少しでも上達させておく事が義務であり、礼儀だとも言えます。
具体的な解決策は?
具体的な対策としては、日常生活の中でちょこちょこと練習するという事です。
長い伝統套路(型)をつなげて練習しようと思えば、時間もかかりますし、スペースも必要となります。
そういったまとまった練習時間やスペースの確保ができないと、人は練習しない訳です。
ですので、一部分だけを切り取って練習するとか、何か気付いた時に一つだけでも練習するとか、そういった事を積み重ねていくしかありません。
実際、まったく何もしないというのと、何か一つだけでも練習したというのは、後々、天と地ほどの差となります。
まったく何も練習しない日が一週間続けば、文字通り、何の進化もありませんが、一週間の間に少しだけでも練習していれば、その分だけでも積立られていきます。
私も若い頃は、毎日2~3時間練習していましたが、人は年齢が上がるにつれ、やらなければいけない事が増えてきます。
その合間を縫って、私もちょこちょこと練習しています。気付けば数時間練習している時もあります。
また武器術などは、武器を持つスペースが無ければ、素手でやりますし、長兵器の場合は、短い棒を利用して行っています。
武術は、商売として教えられない
これは、後に陳式太極拳を学んだ先生も同じような事を仰っていました。
私が根幹的なものを学んだ先生の場合は、ご自身でも教室をやってみて無理だと仰っていました。
そして、私自身も本質的な事まで教えるなら、商売(サービス業)として教えるのは無理だと思います。
その最大の理由は、武術は何をどの段階まで教えるかの判断は、師のほうに絶対的な権限があるからです。
また、そうでなければ、功夫は身に付かないと思います。
狭義的な部分で言えば、型の次の動作を教えるかどうか、あるいは次の段階の練習段階に進めるかどうか、また根本的にその人に教えるかどうかなど、指導に関しての一切の権限は、師のほうにあります。
その生徒の人間性、努力、学ぶ姿勢や態度、取り組み方、上達の度合いなどを総合的に判断して、師のほうが決定します。
それに対し、スポーツクラブやスポーツ教室のように、サービス業を営む場合は、生徒に辞められると困る訳ですから、必然的に生徒の希望や要望に応じたサービスを提供する事となります。
つまり、生徒のほうに権限があります。そこが最大の違いと言えるでしょう。
武術をサービス業として教えると、本人の習熟度とは全く関係なく、生徒の要望に応じた指導をしなければなりません。
そうなってしまうと、結局、本質的な部分をじっくり教える時間はありませんから、文字通り形だけの指導という事になります。
武術界独特の教え
この項目では、私自身が学んでいた時に疑問を感じていた教えや決まり事について紹介します。
実際に中国の武術を学んでいると、「どうして、だめなの?」と思う事も多々あります。
例を挙げると
- 生徒同士が互いに教え合ってはいけない
- 他の人の練習を見てはいけない
- 質問は、先生や指導員以外には、してはいけない
- 学んでいた内容が、途中で中断してしまう
などがあります。
一般的には、分からない事があれば、生徒同士で互いに教え合って、理解を深めるのは良い事でしょうし、人の練習を見る事も参考になるでしょう。
ただし、武術の場合は、前述したように、その生徒に何をどう教えるのかは、全て先生のほうに権限があります。
先生のほうで、この人はもう少し努力が必要だなとか、こちらの指示に従っていないなと判断していても、生徒同士が勝手に教え合ってしまったり、他人の動作を見て覚えようとしてしまえば、その師の判断は全て無効となってしまいます。
また先生や指導員以外に質問をしても、その人が本当の意味で理解していない場合は、本質を見誤る事となります。
これは、鄭志鴻老師の自然道場でも徹底されていました。生徒同士が教え合うのはご法度でしたし、指導は鄭先生が各人に直接行っていました。
ですので、門人同士でも誰が何をどの段階まで学んでいるのかは、未だに分かりません。
陳式太極拳の先生の所でも、拳譜などは、先生から直接受け取っていましたし、やはり徹底されていたと思います。
④ の学んでいた内容(例えば、型など)が、途中で中断してしまうのは、いくつか理由があります。
一つは、明らかに本人の習熟度が追いついていない場合。この場合は、最初に戻ってからのやり直しとなります。
もう一つは、あえて放置して、本人が習熟するまで待つ場合もあります。
例えば、ある套路の前半部分を教えた後は、そのまま本人の習熟度に任せ、一年程度放置した後、基準に達していれば、その套路の次の段階を教える場合などです。
私が刀術や開門拳、二套拳、楊式太極拳を学んだ時もそうでした。
※ 放置期間は、基本功の練習に戻ったり、武器術の基本を習ったりしている事が多かったように思います。
また、一通りの流れを学んだあとに、各段階の要訣に従って学び直す門派もあります。
いずれにしろ、その人にどのような階梯で指導するかは、師の判断という事になります。
では、なぜこのように、指導に対して細かい決まりごとがあるのでしょう?
一言でいえば、それは【武術】だからです。
武術というのは、使い方によっては、人を傷つける道具となり得るからです。
現在、太極拳や八卦掌を学んでいる方のほとんどは、健康法だったり、趣味だったりだと思います。
ただ、その中には、武術として、より厳しい基準の中で学んできた先生もいるでしょう。
そういう先生の場合は、【人を傷つける道具】である事も理解しているでしょうから、指導に際し、慎重にならざるを得ないという事になります。
他門派との付き合い方と礼儀
以前、教えていた生徒から「先日、どこそこの道場に遊びに行ってきました」と言われ、驚いた事があります。
その方の場合は、友人が通っている道場に遊びに行ってみたとの事で、まぁ何事もなかったため、「次回から、他の教室に行く際は、私の許可を取ってからにして下さい」と伝えました。
理由は、何らかのトラブルがあった場合は(どちらかがケガをした場合など)、最終的には道場主同士の責任となるからです。
私も修業時代に他の道場を訪問させて頂いた事があります。
ただし基本的には師の紹介で、師の知り合いの道場に、付き添いで行きました。
その際、事前に礼儀や接し方、また見せて良い内容などについての説明を受けた上で、訪問していました。
空手やボクシング、総合格闘技などの業界では、出稽古が盛んに行われているようです。
ただし、その場合も基本的には、道場主同士のつながりがあっての事だと思います。
中国武術の場合も、基本的には先生の紹介があった上で行ったほうが良いでしょう。
その際、他派の人間と付き合う場合は、通常の2倍の礼儀と謙虚さを忘れない事。
また、お酒の席でも、礼儀を外れないよう注意したいものです。
他流派の経験者の方に
他派の経験者の方で、当会へ入会される方もいらっしゃいます。
その方達には、今まで学んできたものを捨てる必要はありませんが、一旦忘れてほしいとは伝えています。
理由は、一旦リセットをしてもらわないと、当会の技術が身に付かないからです。
他流の経験者の方がよく言われる言葉に以下の二点があります。
- 以前学んでいた先生も同じ事を仰っていました。
- 以前学んでいた先生には、こう言われました。(異なる事を言われた)
いずれの場合も、言葉の表面上の意味が同じか異なるかで捉えるのではなく、本質的な部分を捉えた上で、どう判断するかが重要です。
例えば、本質的には同じ意味の事を言っていても、表現上(言葉)が異なる場合もあるからです。
以前、「一定の基準が身に付いてからであれば、その基準を基に、他派を見る事ができる」と言った事があります。
とはいえ、全てを自らの経験で判断してしまうと、他流である当会の本質的な部分を書き換えて理解してしまう可能性があります。
そのためには、一旦まっさら状態で学んで頂いて、その上で、流派の違いを理解し、最終的に自分が何を修めていくのかを判断してくれれば良いと思います。
まとめ
今回は、伝統太極拳を学ぶ上での心得について、私自身が学んでいた頃の事も思い出しながら、紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。
少し気難しい世界だなと感じた方もいたかもしれません。
ただし、そういった門派だからこそ、学べるものがあるのも事実です。
要は、その方の目的や目標に応じた門派を選べば良いという事だと思います。
当会では、上記で紹介した理由から、サービス業としての太極拳や八卦掌の指導は行っておりません。
商売として割り切って指導できるような、時間的な余裕も場所もないというのが実情です。
教えられる時間も場所も限られていますから、本当に学びたい方のみ、こちらもじっくり指導したいというのが、当会の本心です。
過去に当会で入門者を勧誘した事は、一度もありません。
勧誘して、お客様として来て頂いても、太極拳や八卦掌の本質的な指導ができないからです。
健康法や美容法として学ばれるのも、趣味として学ばれるのも、大いに歓迎致します。
ただし、指導方法は伝統の教え方をさせて頂いています。
(健康法を目的の方に、武術目的の方の基準を押し付けたりはしていませんし、その方の目的に応じた基準を授けています)
この方針は今後も変わりません。
それが、当会の特徴です。
当会での学習を希望される方は、受講案内をご覧下さい。